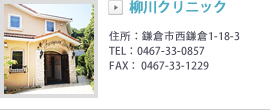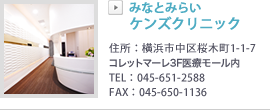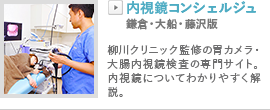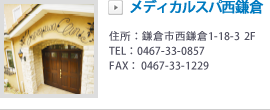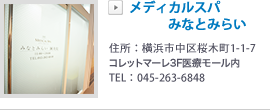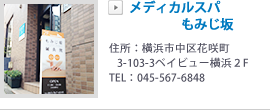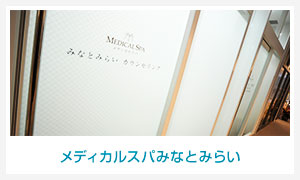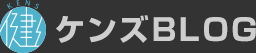鍼灸医学は今から二千年以上前に、古代の中国で誕生しました。
鍼やモグサ(灸)を用いた治療については戦国時代の文献に登場し、身体を流れる気のルート(経脈)に関する記述も紀元前2世紀頃に作られた文献にみられます。
その後、漢代に入ると東洋医学のバイブルである『黄帝内経』が編纂されます。現在の東洋医学の理論もこの『黄帝内経』を基礎としています。
以前某CMに「女性は7の倍数」「男性は8の倍数」の年齢の時に節目を迎え、体に変化が訪れるというものが放送されていました。
これはこの黄帝内経から抜粋されたものです。
人の体の変化では、女性は49歳で閉経を迎えるとあります。現代の女性の一般的な閉経年齢も50歳前後でほとんど変わりません。女性の体が28歳、男性が32歳でピークを迎えるという点においても、現代の医学的な認識とほぼ同じで、医学が日進月歩している現代においても、いまだ二千年前の体の変化が当てはまることが分かります。
鍼灸の知識は6世紀頃、朝鮮半島から日本に伝えられ、平安時代までは灸治療が中心で鍼は外科的な処置を行う際に用いられたようです。戦国時代の武将たちもお灸をすえて戦に赴いたようです。
室町時代後期になると日本でも再び鍼が盛んになり、国内では様々な鍼の流派が生まれていきました。 特にツボ(経穴)と経脈に関する研究は盛んで、江戸初期には経穴に関する学術的な研究書が数多く編纂されます。
また元禄期には盲人の鍼師である杉山検校(けんぎょう)が、将軍綱吉の寵愛を受け、その庇護のもとで盲人に対する鍼灸の教育制度を確立させていきます。
杉山検校は、本名を和一といい、幼いときに失明しました。
鍼医を学んでいましたが、なかなか上達せず、江ノ島の弁財天に参籠します。
そして、満願の日に石につまずいたのがきっかけとなって、「管鍼法」(鍼を管に挿入した状態で刺入する方法)の技術が誕生しました。
石につまずいた和一は、その時に竹筒を拾い、中には松葉が入っていました。
この竹筒の中の松葉が和一の体を刺したことから、管鍼法の技術が考案されたと伝えられています。
この方法は、初心者でも痛みを与えずに刺入しやすいため、 現在でも広く日本で用いられています。
管鍼法の技術を得た和一は、徳川五代将軍綱吉の病を治し、信頼を得て「検校」となります。これは盲官の最高位になります。
和一のつまずいた石が、その後の和一の出世物語にあやかり、以後、ここで物を拾うと 幸運を授かると伝えられ、福石と呼ばれるようになりました。
江島神社の辺津宮へと上る石段の途中に、その「福石」があります。
和一は死後、東京都墨田区の弥勒寺に葬られますが、一周忌に際し、弟子の一人が、ゆかりの深い江の島に笠塔婆型の墓を建立し、灯籠は綱吉の側近である柳沢吉保室が寄進したと伝えられています。
福石の右脇の道を下り朱塗りの橋を渡った所に杉山検校の墓があります。
江の島へ足を運んだ際には、福石にパワーを頂きつつ、傍らにある鍼灸の発展に寄与した故人のお墓を気にとめていただけると幸いです。